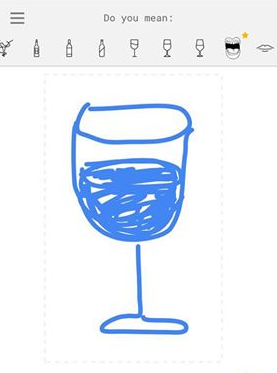2017年
11月
24日
金
セミナー@博多 開催しました
11月23日14:30~、「経営者の為の決算書の読み解き方」セミナーを、
博多駅筑紫口から徒歩3分の会場で開催致しました。
祝日の午後という日程にも拘わらずご参加頂いた皆様、
サポートして頂いたT様とN様、ありがとうございました。
私自身が佐賀県出身であり、博多で開催できたことは本当にありがたいと感じています。
また、今回も参加者の方には何とかバリューを出せたのではないかなと思います。
以下、参加者様のアンケートからの抜粋です。
- 全体の見方が分かってよかったです!
- 基礎的なところを教えて頂き、整理がついた
- 構成や、BS PLの意味がすっきりしました
- 一度触れた内容だが、今回の方が基本中の基本を難しくない言葉で教えて頂けたので理解し易かった
- 今まで何となくで計算していた部分が自分のものにできた気がします
- 分析のやり方が良く理解できました
- この続きでも同じように分かりやすいのがあればぜひ受けてみたいです
- また機会があれば参加したいです!
重ねまして、今回ご縁を頂いた皆様に感謝申し上げます。
またチャンスがあれば、第2回開催も前向きに考えたいと思います ^ ^
2017年
10月
19日
木
セミナー@博多 開催します!
これまで名古屋で開催していた「経営者の為の決算書の読み解き方」セミナーを、
オープン開講としては初めて、博多で開催致します。
11/23(木・祝)、14:30~17:30、博多駅すぐの会場です。
自社の決算書を片手に、細かいことは大胆に省略した上で、「決算書の全体像」を掴んでいただけます。
過去、殆ど全ての参加者の方から「分かりやすい!」とご評価を頂いてきたセミナーです。
「財務の重要性は分かっているんだけど、、、」という経営層の方で、以下に当てはまる方に特におススメです!
・ 利益と現金の違いが分からない(利益が出ればお金が増える、と思っている)
・ 減価償却費がどういうものか、何度聞いてもモヤモヤする
・ 決算書を読む学習にはチャレンジするが、専門用語が多く、いつも挫折する
・ 損益計算書(PL)は何となく分かるが、貸借対照表(BS)がナゾの存在。
・ 税理士や銀行員と引け目なく話ができる様になりたい
・ 会社を強くする為には節税が一番だ、と思っている
・ なぜ「自己資本比率は高い方が良い」と言われるのかが分からない
・ 簿記は学んだが、決算書の読み方は学んでいないし分からない
・ 税理士の話がいつも今一つ理解できない
セミナー詳細 及び申し込みはコチラから!
過去の開催の様子はコチラ。
終了後に(希望者のみ)懇親会アリ、です。
「気になることは今年の内に!」
福岡及び近辺の方のご参加をお待ちしております。
2017年
6月
16日
金
企業研修実施しました!
昨日、千葉県某所で「財務会計とリーダーとしての意思決定」というタイトルにて企業研修を実施致しました。
従業員数10万人に迫る、一部上場の重厚長大産業のグループ会社様での、
トータル3日間に及ぶ研修の内、財務に充てられた5時間を担当。
対象者は、30歳前後~50歳前後、かつ職種も、経理課の方からクレーン係の方まで様々。
前提が揃っていない分、コンテンツの絞りどころが中々難しい部分はありましたが、
・ 図や写真を多用し
・ PLとCSからの企業あてクイズや、ジャニーズ事務所での芸能人のマッピング(PPM: Product Portfolio Management)などを盛り込み
・ 財務初めての方には興味を持って貰えるように
・ 財務に触れている方には、経営者視点を持ち、経営戦略との繋がりが分かるように
コンテンツを作りこみ、グループディスカッションを多めにとるなど進行にも工夫しました。
項目としては
1. BSとPLの理解
2. 経営戦略とCash Flow
3. 財務分析の勘どころ
4. 株式と企業グループ
5. 管理会計:損益分岐点分析
といった内容でした。
終了後、人事管轄の役員の方と研修会社の方からは嬉しいフィードバックを頂き、
また受講生の方からも「財務の扉をノックすることができた」「ユーモアがあり説明も理解しやすかった」
「なるほどと感じることができた」というご感想を頂きました。
ご依頼頂きました企業様及び研修会社様、ご縁を頂きましたM様、どうもありがとうございました!
2017年
5月
08日
月
セキビズにて相談会を実施しました
GWのあいまに、岐阜県関市が運営する関市ビジネスサポートセンター(通称セキビズ)にて、
財務に関する相談会を実施しました。
業績が思うように回復しない局面において銀行の見方がわからず不安になっている方や、
今後拡大していくにあたり、どの様な考えや基準で資金を調達すれば良いかという
ご相談などをお受けしました。
業種も規模も様々でしたが、何とかバリューを出せたのではないかと思います。
ご相談くださった皆様、杉山センター長をはじめとした関ビズの皆様、
貴重な機会を頂きありがとうございました。
ご相談をお受けして、やはり「銀行の見方」を伝える事の重要性をひしひしと感じました。
債務償還年数、自己資本比率、格付と貸倒の引当など。
ネットを見ればヒットする情報ではあるのですが、やはり中小企業の経営者にとって、
そこにリーチすることとそれを理解することのハードルは中々の高さ。
この内容については、近い内に書きたいと思います。
2017年
11月
24日
金
セミナー@博多 開催しました
11月23日14:30~、「経営者の為の決算書の読み解き方」セミナーを、
博多駅筑紫口から徒歩3分の会場で開催致しました。
祝日の午後という日程にも拘わらずご参加頂いた皆様、
サポートして頂いたT様とN様、ありがとうございました。
私自身が佐賀県出身であり、博多で開催できたことは本当にありがたいと感じています。
また、今回も参加者の方には何とかバリューを出せたのではないかなと思います。
以下、参加者様のアンケートからの抜粋です。
- 全体の見方が分かってよかったです!
- 基礎的なところを教えて頂き、整理がついた
- 構成や、BS PLの意味がすっきりしました
- 一度触れた内容だが、今回の方が基本中の基本を難しくない言葉で教えて頂けたので理解し易かった
- 今まで何となくで計算していた部分が自分のものにできた気がします
- 分析のやり方が良く理解できました
- この続きでも同じように分かりやすいのがあればぜひ受けてみたいです
- また機会があれば参加したいです!
重ねまして、今回ご縁を頂いた皆様に感謝申し上げます。
またチャンスがあれば、第2回開催も前向きに考えたいと思います ^ ^
2017年
10月
19日
木
セミナー@博多 開催します!
これまで名古屋で開催していた「経営者の為の決算書の読み解き方」セミナーを、
オープン開講としては初めて、博多で開催致します。
11/23(木・祝)、14:30~17:30、博多駅すぐの会場です。
自社の決算書を片手に、細かいことは大胆に省略した上で、「決算書の全体像」を掴んでいただけます。
過去、殆ど全ての参加者の方から「分かりやすい!」とご評価を頂いてきたセミナーです。
「財務の重要性は分かっているんだけど、、、」という経営層の方で、以下に当てはまる方に特におススメです!
・ 利益と現金の違いが分からない(利益が出ればお金が増える、と思っている)
・ 減価償却費がどういうものか、何度聞いてもモヤモヤする
・ 決算書を読む学習にはチャレンジするが、専門用語が多く、いつも挫折する
・ 損益計算書(PL)は何となく分かるが、貸借対照表(BS)がナゾの存在。
・ 税理士や銀行員と引け目なく話ができる様になりたい
・ 会社を強くする為には節税が一番だ、と思っている
・ なぜ「自己資本比率は高い方が良い」と言われるのかが分からない
・ 簿記は学んだが、決算書の読み方は学んでいないし分からない
・ 税理士の話がいつも今一つ理解できない
セミナー詳細 及び申し込みはコチラから!
過去の開催の様子はコチラ。
終了後に(希望者のみ)懇親会アリ、です。
「気になることは今年の内に!」
福岡及び近辺の方のご参加をお待ちしております。
2017年
9月
14日
木
エストニアに法人を設立しました
世界最先端のIT国家エストニアに、法人 Sunbows Estonia OU を設立しました。
2016年6月の視察訪問の時から、国としてのポテンシャルには本当に驚かされてきました。
知れば知るほど面白い国、エストニア。例えば…
・ほぼ全ての行政手続きがオンラインで可能
→土地や法人の登記、投票、住所変更 etc(結婚と離婚だけは足を運ぶ必要あり)
・クリック3回で確定申告完了。電子納税率99%、インターネットバンキング99.8%
・eIDで個人の病歴、服用薬やアレルギーが分かる為、救急車で運ばれてもすぐに適切な治療に入れる
歴史的背景として、
・1991年にソ連より独立。旧ソ連の人工知能研究所がエストニアにあった
・独立当初からICTとバイオに資本集中(学校の屋根の修理よりPC購入を優先した)
・Skypeがエストニアで生まれ、人材が育ち資金が集まり、国内で還流している
などなど。
更に、法律行為がe-ベースでできる為、例えば日本に居る私のエストニア法人と、
ブラジルに居る誰かのエストニア法人が、エストニアの法律に従って、
オンライン(電子署名)で何等かの契約を締結することも可能になります。
一度も会わずに。現地に行かずに。
EU圏内の法人となることもプラスです。
小学校ではプログラミングが義務化されていたり、
既にブロックチェーンが教育の場に登場していたりと、
残念ながら日本とは隔世の感があります。。。
最近になってエストニアの露出が増えてきました。
② エストニア共和国”世界初"国がICO計画 新規仮想通貨公開トークンエストニア
今回の法人設立も、e-residencyの仕組みを使って、現地を訪問することなく、
オンラインで電子署名を行うことによって完結できました。
このe-residencyも、国として「ひとまず制度を作り、使い方はその後のアイデアソンで募った」
という振り切り方。ポテンシャルの塊です!
2017年
6月
16日
金
企業研修実施しました!
昨日、千葉県某所で「財務会計とリーダーとしての意思決定」というタイトルにて企業研修を実施致しました。
従業員数10万人に迫る、一部上場の重厚長大産業のグループ会社様での、
トータル3日間に及ぶ研修の内、財務に充てられた5時間を担当。
対象者は、30歳前後~50歳前後、かつ職種も、経理課の方からクレーン係の方まで様々。
前提が揃っていない分、コンテンツの絞りどころが中々難しい部分はありましたが、
・ 図や写真を多用し
・ PLとCSからの企業あてクイズや、ジャニーズ事務所での芸能人のマッピング(PPM: Product Portfolio Management)などを盛り込み
・ 財務初めての方には興味を持って貰えるように
・ 財務に触れている方には、経営者視点を持ち、経営戦略との繋がりが分かるように
コンテンツを作りこみ、グループディスカッションを多めにとるなど進行にも工夫しました。
項目としては
1. BSとPLの理解
2. 経営戦略とCash Flow
3. 財務分析の勘どころ
4. 株式と企業グループ
5. 管理会計:損益分岐点分析
といった内容でした。
終了後、人事管轄の役員の方と研修会社の方からは嬉しいフィードバックを頂き、
また受講生の方からも「財務の扉をノックすることができた」「ユーモアがあり説明も理解しやすかった」
「なるほどと感じることができた」というご感想を頂きました。
ご依頼頂きました企業様及び研修会社様、ご縁を頂きましたM様、どうもありがとうございました!

2017年
5月
08日
月
セキビズにて相談会を実施しました
GWのあいまに、岐阜県関市が運営する関市ビジネスサポートセンター(通称セキビズ)にて、
財務に関する相談会を実施しました。
業績が思うように回復しない局面において銀行の見方がわからず不安になっている方や、
今後拡大していくにあたり、どの様な考えや基準で資金を調達すれば良いかという
ご相談などをお受けしました。
業種も規模も様々でしたが、何とかバリューを出せたのではないかと思います。
ご相談くださった皆様、杉山センター長をはじめとした関ビズの皆様、
貴重な機会を頂きありがとうございました。
ご相談をお受けして、やはり「銀行の見方」を伝える事の重要性をひしひしと感じました。
債務償還年数、自己資本比率、格付と貸倒の引当など。
ネットを見ればヒットする情報ではあるのですが、やはり中小企業の経営者にとって、
そこにリーチすることとそれを理解することのハードルは中々の高さ。
この内容については、近い内に書きたいと思います。

2017年
4月
25日
火
CFOの矜持
先日、友人がSNSを通じてある記事を紹介してくれました。
6ヶ月後に会社が潰れるのが確実になった時、ベンチャー企業のCFOがやるべきこと 【とあるCFOの独白】
記事を書いた方が経験を共有して下さったことに感謝と敬意を表すと共に、中小企業の社外CFO的な立場に居る私にとって、思うところ多々ある記事でした。
私は数年前、取締役を事実上解任されたことがあります。
ベンチャーのステージを過ぎた、年商数十億の同族企業で起きたことです。とある事情でやり手創業者オーナーから親族に経営をバトンタッチせざるを得ない事となったその会社で、当初私は資金繰りサポートの為にパートタイムで関わったものの、業績の落ち込みと共に関与を増し、ついには取締役となってターンアラウンドを実現する、という役割を担うことになりました。
返済条件緩和を伴う資金繰りと銀行折衝、部門別会計の構築と運用、KPIの設定、元帳の洗い出しから削減すべき経費の特定などのCFO業務に加え、意思決定方法や情報伝達方法も変更。又、経営陣と現場との間に距離を感じた私は、現場で何が起きているか、最前線の従業員がどんなマインドで働いているかを知る為に、一人30分~1時間、トータル3~4日かけてパートの方も含め全員と面談しました。ベクトルを合わせる事を主眼に、賞与の査定表や社内報の作成、拠点長会議のファシリテーション、全従業員が参加する総会のプロデュースまでも行い、現場のグリップ感も感じながら、CFOという立場を超えて、参謀役として一つ一つ着実に物事を変えていきました。
会社の待ったなしの状況に突き動かされつつ、その経営状況への解釈に私とは温度差がある親族経営者との間合いも意識しながら、彼らにとって単に耳が痛い話だけでなく、襟を正すだとか、身を削る様な話も俎上に乗せ…。仕事に対するやりがい、身に着けた事を発揮できる環境の有難さと共に、親族経営者に対する「じれったさ」も感じていました。
そんな中、思いもよらぬ事件がおこりました。役員会の席で、同席した弁護士から開口一番、「辞任せよ」という通告を受けたのです。親族経営者からの働きかけによる言葉なのは明らかでした。
推察するに、やはり会社を立て直す為に親族経営者に提示した「自身の身を切る」ということの必要性を、腹の底からは理解してもらえていなかったのでしょう。これについては勿論、私自身の説明能力の乏しさ、物事を進める際の感情面への配慮が不十分だったこと、は否めません。しかし、身を切る事自体、あの状況下では避けて通れない道でした。
・・・自分は何に従って仕事をしてきたのか。「会社の為に」よかれと思った事をつらぬいてきた。たとえそれが「経営者一族の為」ではなくても、自分の判断軸に従って、「会社の為」と思えることは率先してやってきた。「会社」とは、ステークホルダーのバランス、つまり株主や経営者に限らず、顧客、取引先、債権者、従業員の為でもある・・・。
ここで、「この顧問先を離れるのか、頭を下げて残るのか」という選択が生じます。
頭を下げれば引き続き仕事ができ、収入も継続する。しかしそれは、CFOとしての自分の軸を曲げる事にもなるし、仕事の仕方も変えなければならない。業績改善の実現性も遠のく。果たして…。
「根底の思いや姿勢がこうも違う経営陣とは、長くは一緒に働けない」「しかし、今まで報酬をもらっていた恩もある」「いやいや、それ以上の価値は絶対に提供してきた自負はある」「従業員の期待を裏切るのはツライ」…
色んな思いが交錯した中で学んだことは「誰と仕事するかは、本当に大事」という事。
CFOの立場では、必ずと言ってよいほど経営者と衝突する場面に遭遇します。私自身、CFOとして、意見が相違した場合の判断基準について頭を巡らせてきました。ずっと疑問に思い、本を読み、ディスカッションし、質問をぶつけようやくたどり着いた私自身の解は、「経営者が事業を通じて作りたい/変えたいと思っている世界に賛同できるかどうか」「それに沿った意思決定がされているかどうか」という事です。
経営上の一つ一つの意思決定は、北極星を目印にして航海する舟のオールを漕ぐようなもの。同じ舟に乗り、同じゴールを目指している限り、その中での衝突は乗り越えられるのだと信じます。会社の進路を誰よりも数字で理解しているCFOにとって、舵取りがこれに大きく反することが明らかな場合は、CFOは全力で経営者を止めることになるのだと、私自身は考えます。そして、進みたい方向に賛同できない場合、CFOは舟を降りるべき。そもそも、その舟に乗ってはいけない。そう思います。
その会社の親族経営者と、方向性、もっと言えば世界観を共有できていなかった私は、結局、「乗る舟を間違えた」という思いと、「本当に力のある人ならば、こんな環境でも会社を変えられるハズ」という自分自身の実力不足も感じながら、志半ばで結局辞任を決意。このままこの体制のこの立場で努力しても、たぶん成果は上げられない。従業員には申し訳ないが、全てを得られるワケでない…。そうした忸怩たる思いで、会社を去ることになりました。
経営者が何を重視し、どんな世界をつくろうとしていて、そのために何を犠牲にしても良いと思っているか。どんな優先順位なのか。財産や収入、メンツ、社会的地位、、、。いよいよという場面では、このあたりが見え隠れします。勿論、方法論での意見の相違は茶飯事ですが、ギリギリの局面における意思決定では、世界観を握れているかどうかがカギになる。そういうことを再認識させてくれた記事でした。
2017年
4月
19日
水
セキビズ(岐阜県関市)で相談会を実施します
この度、岐阜県関市の「関市ビジネスサポートセンター」からお声がけ頂き、
「特別金融相談会」と銘打って、中小企業の経営者の方を対象に、
「特別相談員」として資金繰りに関するご相談をお受けします。
※ スクロールすると該当するイベントが出てきます
今回、ご縁あって公的機関から初のご依頼を頂き、実施させて頂くことになりました。
5組限定(先着順)ですが、お金を貸す銀行の立場、
お金を借りる企業側の立場の両方を経験している身として、
精一杯お役に立ちたいと思います。
2017年
4月
13日
木
google auto draw
4月11日にgoogleが公開した Auto Drawが一部で話題になっていますね!
テキトーな落書きを、自動でプロレベルのイラストに仕上げてくれるというもの。
プレゼンツールとして大活躍しそうです。
例えばこんな風に変換できちゃいます!
2017年
4月
03日
月
Fin-tech, Block-Chain, AI ...
苦手だったテクノロジー分野に関して、「もはや避けられない!」との思いに強烈に襲われ、fin-tech,block-chain, AIそれぞれ、別のグループや勉強会に参加し(地域も、名古屋、東京、オンラインとさまざま!)、今年から勉強しています。
余談ですが、先日実家に帰った際、75歳でスマホ利用中の両親に、クックパッド・google翻訳・LINEのりんな(人工知能)を教えたら、母はクックパッドに、父はりんなに熱中・・・ ^ ^; でもまぁ、テクノロジーの進化に、両親ともに感動しきり、でした。
しかし、知れば知るほど、聞けば聞くほど、テクノロジーの爆発力には驚愕します&ワクワクがとまりません!
例えば・・・
l イーロンマスクが、人間の脳にAIを接続することを目指す法人を設立
l スカイプで英西伊中などの自動通訳機能が実装されて、異言語コミュニケーションが容易に。通訳の仕事が激減。(参考You-tube )
※ 日本語も、google翻訳で一定言語との通訳、翻訳(音声、テキスト共)は既に実現
l 三菱東京UFJ銀行が、ブロックチェーン技術により仮想通貨MUFGコインを開発中
⇒ 日銀が管理する貨幣(日本銀行券)ではない通貨を銀行が持つことに?
l テキスト(文章)を与えることで、AIが画像を(ネット等から引っ張ってくるのではなく)「作り出す」事が可能に。肖像権や著作権などが問題にならなくなる?
l 音声認識技術とAIによる読唇術のあわせ技で認識率が99%に。カーナビに実装され、手を使わなくても操作可能に。
l 画像認識技術で表情を読み取り、その人の感情やウソが分かるように
⇒ 映画やCMの反応分析が可能に。マーケティング等への応用が期待されています。
l AIがネットバンキングのデータを吸い上げ、他社データや自社の履歴から、会計上の仕訳を予測して会計処理をレコメンド(実装済み。広がりつつあります。)
今のところ、実用化されているのはある機能に特化した「特化型AI」のみで、ドラえもんの様な「汎用型AI」の実現はまだまだ先と言われていますが、今我々が大きな転換点に居ることは間違いありません。
ビジネスにおいては、アマゾンが街の本屋のシェアを侵食する以上の変化がどの業界においても日常的に起きてきます(既に起きていますし、間違いなく加速していきます)。
「AIが仕事を奪う」「いや新たな仕事ができるだけ」と、それぞれ意見がありますが、AIは意思を持たない道具です。このまま行けば「AIを使う/コントロールする人」と「AIに使われる人」が二極化し、格差が広がることはほぼ間違いないでしょう。これは、個人でも法人でも言えることだと思います。
Fin-tech, Block-chain, AIに関して、まずとっかかりが欲しい方、壁打ちしたい方は、遠慮なくご連絡下さい。楽しく会話しましょう ^ ^
2017年
3月
19日
日
事業性評価ツールのご紹介(経産省公表)
先日、経産省より、「ローカルベンチマーク(通称ロカベン、らしいです)」なるものが公表されました。
経営者の方は、ざっとで良いので、一度目を通されることをお勧めします。
このツールの狙いとして、
・経営者、金融機関、支援機関が企業の状態を把握(企業の健康診断)し、目線を揃える
・事業性評価(後述します)の入り口としての活用を期待
と書かれており、更に、
・「財務情報」と「非財務情報」入力により経営状態の変化に早めに気づく
注)財務情報 :売上高増加率など6つの指標
非財務情報:経営者、関係者、事業、内部体制の4つの指標
・早期の対話や支援に繋げていく
と述べられています。
現在の「決算書の分析」と「担保・保証」中心の金融機関の姿勢が、
今後は定性部分の「事業性評価」を考慮したものに変わっていきます。
尚、ここには経営分析の基本的なフレームワークがちりばめられているのが分かります。
(バリューチェーン、5Fなど)
この事業性評価、今までも「定性面評価」として金融機関の審査内容としては存在しましたが、
事実上は殆ど機能しておらず、「定性部分は殆ど加味しない。定量のみ。」と断言する
地方銀行もあったほどです。
恐らく、判断の基準が難しい(人によってブレる)、銀行自体に事業を評価するノウハウが乏しい、
という事情があったのではないでしょうか。
金融庁に森長官が就任されてからこの金融機関の審査姿勢(より根源的には存在意義)が
問われ続けてきたワケですが、今回は(経産省の公表とはいえ)
それがかなり具体的な形になって公表された、と考えて良いのではないかと思います。
【参考サイト】
地域金融機関による事業性評価について(平成26年10月 金融庁)
冒頭に掲げたロカベンは経産省ですが、「事業性評価」の比重が
今後重みを増してくるのはほぼ確実です。
余談ですが、金融機関も「オーバーバンキング」と言われて久しく、
金利収益も取りにくい状況て、特色の出せない銀行は淘汰される局面に
既に入っていると考えて良いと思います。
「水は、高い方から低い方に流れる。」
金融機関の審査に関しても、上記の様な方向には(早い遅いはあれど)
移行せざるを得なくなってくるでしょうね。
使い方が分からない、ディスカッションしながら作りたい、という経営者の方は
お気軽にご連絡下さい。
2017年
1月
16日
月
エストニアセミナー開催しました
1月15日(日)、エストニアセミナー開催しました。
ご参加の皆様、雪の降る中お越し頂きありがとうございました。
中には東京からわざわざこのセミナーの為だけに足を運んで頂いた方もいらっしゃいました。
今回、エストニア在住でマネーフォワード始め公官庁や学校などで
多数の講演実績のある小森さんにご講演頂きました。
参加された方の興味としても、電子政府、投資、税制、欧州取引や進出のみならず、
教育、移住などにも及び、エストニアを知るという意味では入口として
Fit感のある内容ではなかったかと思います。
私自身、昨年6月に現地を訪れ、国としてのポテンシャルをまざまざと感じてきたところです。
率直な感想としては「日本ヤバい…」です。
国としての効率化、子供の頃からのエンジニアリングや起業の教育、
母国語ではない英語の通用度合い(ほぼ100%)などなど。
今回のセミナーで、エストニアの概要と、ひるがえって日本の立ち位置を考える材料を
いくらか共有できたのではないかと思います。
重ねまして、ご参加の皆様、ありがとうございました。
又、ご興味あるお方がいらっしゃれば個別にご連絡下さいませ。
2016年
12月
06日
火
1月15日(日) エストニアセミナー実施します!
なぜエストニア?とお思いの方も多いと思います。
実はエストニアは、以下の様な特徴を持つ、とても興味深い国なのです。
① 税制がシンプルで、個人の確定申告はクリック3回で終了
② 法人登記はオンラインにより20分足らずで完結!訪問不要。
③ 法人税率0%(但し配当時に法人に20%課税)
④ 役員の要件等もなく、会社維持コストが極めて低い
⑤ EU圏内であり、EU内の取引は関税不要、送金手数料1ユーロ以下
⑥ 電子政府として世界最先端。IDにより殆どの行政サービスはオンラインで可
⑦ Skipeを生んだ国であり、IT立国。スタートアップ(起業)が盛ん
⑧ EU圏内で唯一国債未発行であり、財政が健全
⑨ 若い(小学生くらいの)頃から起業やプログラミングへの教育が手厚い
⑩ 母国語ではない英語がほぼ完全に通じる
その他諸々…
私自身、2016年6月に現地視察に行き、日本とのあまりの違いに驚愕するとともに、強く思ったのが「日本やべぇ…」です。日本に留まっているだけ、もしくは普通に海外旅行しているだけでは決して分かりえない、現地の「国としての取り組み」を知り、「このまま日本に居て良いのか?」とさえ思いました。
そんな驚きの国、エストニアのセミナーを今回開催することになりました。講師はマネーフォワードや明治大学でも公演実績のある、現地在住の小森さんです。
※詳しくはリンク先をご覧下さい。
ブレグジット以降、EUにおいて英語がほぼ完全に通じるエストニアの存在感が増してきています。以下の項目にピンとくる方は、ぜひこのセミナーへの参加をご検討下さい。
① 海外進出を考えたい・EU内企業との取引がある
② 海外への資産移転や資産保護に興味がある
③ 世界最先端の情報をナマで聞きたい
④ スタートアップ(起業)の環境を知りたい
⑤ 将来の産業構成(特に士業)がどうなるのか、材料が欲しい
⑥ 子供の留学先を考えている
関心のある方であればどなたでも参加可能です。無料です。
尚、投資の勧誘等の営業活動は行いませんのでご安心下さい。
2016年
4月
01日
金
企業研修 実施しました!
今日から新年度ですね!新入社員を迎え、研修のシーズンでもありますね。
当社は先日、静岡県内の製造業(売上数百億)の企業さまにて、「経営者の為の決算書の読み解き方」の企業研修を実施致しました。地元近隣業種の上場企業の決算書を見本として、創業以来の利益の蓄積はどこを見れば分かるのか、減価償却費とは何か、という事を、主に図を使って説明致しました。今回は、経営層でも経理部門でもなく、外部取引先から決算書を受領する立場の部署の方に向けての開催でした。今回も「分かり易い!」というお声を数多く頂きました。以下、参加者様のご感想(抜粋)です。
-
今まで苦手意識が強かった私でも、大変分かり易く、あっという間の3時間でした。こんな充実したセミナーは初めてというくらいです。資料も分かり易く、参加できて良かったです。ありがとうございました。
-
他のセミナーと違い、実際に手を動かして学ぶことが出来て良かった。個人的な意見では、3時間では足りない為、質問時間含め所要時間として1日くらい必要だと感じた。
-
我々のレベルに合わせて、ていねいに分かり易くご指導頂きましてありがとうございました。また第2弾を検討させて下さい。
-
簿記が苦手で高校も挫折ばかりでしたが、楽しく学べる事が出来ました。仕入先の見方が変わりそうです。
-
丁寧なご指導ありがとうございました。財務分析の勘ドコロの絵による解説が分かり易かったです。
-
決算書等、初めて触れることばかりでしたが、大変分かり易く教えて頂けました。今後、もう少し踏み込んだお話も聞いてみたいです。
企業研修、承ります。詳しくはお問い合わせ下さい!
2016年
2月
06日
土
セミナー「経営者の為の決算書の読み解き方」開催しました!
本日、「経営者の為の決算書の読み解き方」を開催致しました!会場は前回と同じ、オフィスパーク名駅プレミアホール。立地も良く設備が整っていて、綺麗な会場です ^ ^
今回は、事業承継ご予定の方、女性経営者、上場企業にお勤めの方などに加え、税理士や現役銀行員、会計事務所にお勤めの方など、財務・会計・税務分野の専門家にもご参加頂きました。現役銀行員から皆さんに「こういう見方をするよ!」というコメントも頂けたりと、得感の高い回になったのではないかな、と思います。
参加者様の声を一部、共有させて頂きますね。
・ 細かな数字の計算ではなく、イメージで大きな流れやチェックのポイントが説明されていたので、とても分かり易かったです。
・ あいまいに理解したままにしていた部分の理解が深まりました。現経営者が父なのですが、数字などを使って論理的に進言ができるようになったと思います。
・ 予備知識も殆どない状態でのセミナーでしたが、分かり易い説明でした。自社の自己資本比率を知りたいなど、BS、PLに興味ができました。
・ 途中からの参加でしたが、大変分かり易く、家庭の例をPL、BSに表現することで、理解のスピードが早まりました。
・ とても良く分かりました!色々な企業さんの決算書が読みたくなりました。
・ 自己資本比率のもやもやが晴れました。すとん、と落ちました。
・ 疑問に思っていた事が解決しました。忘れない様に復習します!
・ 現金≠利益の理解がとても重要。非常に分かり易かった!
・ 個人の話にかえての説明がとても分かり易かったです。同じテーブルの方との話もすごく楽しかったです。
・ 短時間で自分の会社の財務が分かる様になりました。
・ 全体的な感覚は掴めた。特にBS、PLに関しては多少なりとも説明できると思う。今後、BS、PLをしっかり分析し、店舗運営に役立てたい。
次回の開催は今のところ未定です。個別開催(出張セミナー)は承りますので、ご希望の方はご連絡下さいね!


2015年
12月
28日
月
セミナー開催します(2/6土)
自社の決算書を片手に、細かいことは大胆に省略し、「決算書の全体像」を掴んでいただくセミナーです。
「平日は時間調整難しい」という声にお応えして、初の土曜日開催です。
「財務の重要性は分かっているんだけど、、、」という経営者で、以下に当てはまる方におススメです!
・ 利益と現金の違いが分からない(利益が出ればお金が増える、と思っている)
・ 減価償却費がどういうものか、何度聞いてもモヤモヤする
・ 決算書を読む学習にはチャレンジするが、専門用語が多く、いつも挫折する
・ 損益計算書(PL)は何となく分かるが、貸借対照表(BS)がナゾの存在。
・ 税理士や銀行員と引け目なく話ができる様になりたい
・ 会社を強くする為には節税が一番だ、と思っている
・ なぜ「自己資本比率は高い方が良い」と言われるのかが分からない
・ 簿記は学んだが、決算書の読み方は学んでいないし分からない
・ 税理士の話がいつも今一つ理解できない
2月6日(土)10:00~13:00、名駅プレミアホール(名古屋駅徒歩3分)にて。
セミナー詳細はコチラ
前回開催の様子はコチラ
2015年
12月
14日
月
福岡でセミナー開催致しました!
先日、縁あって福岡市内で「経営者の為の決算書の読み解き方(90分の短縮version)」を開催致しました。少し前に九州の顧問先の社長あてにマンツーマンでセミナーを行った所、大変ご評価頂き、「知り合いの社長たち向けにもぜひ開催してくれ!」とご依頼頂いた事がきっかけになりました。
30名が余裕で入る社長のペントハウスを会場に、福岡の夜景を見下ろしながら、通常の内容をギュギュッと凝縮してお伝え致しました。多くの中小企業の社長に加え、大手証券会社や地方銀行の支店長クラスの方も(受講ではありませんが)ご参加下さいました。
終了後すぐに懇親会というスケジュールの都合上、アンケートは省略しましたが、その懇親会の場で、複数の方から「今日はホンットにに分かりやすかった!(声に力を込めながら)」「大変参考になった(お辞儀されながら)」「良かった!勉強になった(にこやかに笑いながら)」、金融機関の方からは「皆さんの反応を見て、こういう伝え方をすれば良いんだな、と感じた」と直接フィードバック頂けたことに加え、次回以降に繋がりそうな話も頂戴しました。
現在継続的に開催している当セミナーはベーシックな内容なのですが、多くの経営者の方にとって、断片的な知識が一つの線となって繋がり、「そういうことだったのか!」と気付きが得られる内容となっております。こちらとしても、経営者の方がどこでつまずかれているのか、確信を持って参りました。
さて、次回は来年、2月6日(土)10時~13時で、名古屋駅近くにて開催致します。初の土日開催です。近日中に正式にご案内致しますね!
※ 日程合わない方、個別にセミナー開催致します。詳しくはお問い合わせ下さい。

2015年
11月
12日
木
2015年を代表する女性起業家にお会いして来ました

以前に学んだアントレプレナーファイナンス実践塾 の繋がりで、株式会社ファーストブランド様(大阪) を訪問してきました!
ファーストブランド社の河本社長は、銀行員を経て外資系航空会社でCA(キャビンアテンダント)として勤務された後、IT業界で起業されたという、面白い経歴をお持ちの方です。
数々の賞を受賞されており、本日現在も新日本有限責任監査法人様開催の、2015年を代表する女性起業家を決める女性経営者表彰制度 「EY Winning Women 2015」 にて、ファイナリストとして表彰式に出席されています。(審査員の一人がLINE元社長の森川氏です)
銀行出身者でありながら、自分が自由に動けるように一人目の社員としてCFOを採用されたことや、リーマンショック後の難局での資金調達、スキルよりも理念に合うかどうかを徹底的に追求した人材採用の姿勢など、興味深い話が盛りだくさん。管理部門トップである仲副社長とは、NHKドラマのハゲタカの話で熱く盛り上がりました!次世代幹部候補の川添さん、ご調整ありがとうございました!
2015年
11月
06日
金
M&A案件、ご成約頂きました!
売り手様側のファイナンシャルアドバイザー(FA)として春ごろから取り組んでおりましたM&A案件が、先日無事クロージングを迎えました!
売り手様は福祉事業を営む株式会社で、若手の創業社長が家庭の事情他の理由で売却をご希望されておりました。
買い手様は、愛知県内で中古品のリサイクル業を営みながら、近年進出されたデイサービス事業の立ち上げが落ち着かれたタイミングで、次の一手を探しておられました。こちらも30代の若手社長。
異業種ながらビジネスモデルとしては近しいものがあり、親和性の高いマッチングと言えます。規模的にはコンパクトながら、色々なドラマがあり、取り組みがいのある案件でした。今回、売り手サイドのFAとして、バリュエーション、NDA(守秘義務契約)からノンネームシート及びIM(Information Memorandum)の作成、買い手候補の選定及び接触、価格交渉、基本合意書の作成、最終契約書の作成及び調印式まで、一気通貫して全て当社で実施させて頂きました。加えて、今回の買い手様の社長は元々財務に詳しい事、及び当社を完全に信頼して頂けた事からFAを立てられず、ご自身でやりとりをして頂けた為、先方に代わって実質的なDD(デューデリジェンス)も行わせて頂きました。
M&Aは実行した後(いわゆるPMI)が勝負ではありますが、ともかくも無事にクロージングを迎えられた事に、当事者様と共に喜んでおります。この様な機会を持たせて頂きました売り手様及び買い手様には感謝の言葉しかありません。本当にありがとうございました。
思うに、小規模のM&Aニーズは、恐らく市場に数多あるのではないでしょうか。今回はM&Aありきという話ではなく、財務アドバイザーとして関わっていた顧問先様からたまたまご相談頂いた事から案件がスタートしました。それも元々は、売り手様社長と弊社取締役の渡辺との個人的な繋がりからお声がけ頂いたという経緯です。
M&Aをお考えの企業様は銀行や税理士の方にご相談されたり、ネットで業者を検索される事が多いと思いますが、フィーが高額になるケースが多くあります。特に大手に依頼された場合、株式の売却代金が3,000万円なのに、手数料が1,000万円、という事例も珍しくありません。
当社はM&A専門会社ではありませんが、その分、M&Aに拘らずに幅広いご提案及び業務提供ができると共に、フィーについてもご納得できる金額でご提示させて頂きます。立ち位置としては、あくまで参謀です ^ ^
という事で、売り手様及び買い手様、貴重な機会を頂き、ありがとうございました!
2015年
11月
04日
水
セミナー「経営者の為の決算書の読み解き方」第2回開催致しました!
会場はオフィスパーク名駅プレミアホール。手ごろな広さで設備が整っていて、綺麗な会場でした ^ ^
上場企業、事業承継を予定されている方、起業された方、女性経営者など、多数の経営者の方にお越しいただきました。業種も、流通業、製造業、IT、医療系など様々。オーダースーツサロンの経営者の方もいらっしゃいました。税理士事務所からもご参加頂きました!
参加者様の声を一部、共有させて頂きますね。
【参加者様のご感想(抜粋)】
・ とても勉強になり、非常に満足しております。大事なポイントが「なぜ大事なのか」という点が理解できました。今日学んだ事を実務、経営にどう活かせるか…楽しみです(M様)
・ 減価償却や借入金の概念が理解できたのが収穫です。PLとBSの変化を体験できたのが良かったです。(鳥羽様)
・ 簿記を少し習った事があり、点・点の知識はあったが、本日お話を聞かせていただいて、それがつながったような気がします。(T様)
・ 基本レベルをとらえながら、より分かり易く丁寧に教えて頂けて、数字の繋がりを理解できました。利益=現金ではない事もすんなり理解できました。(須藤様)
・ 問題を解きながらだったので、理解できているか確認しながら進めて行く事ができて、しっかりと自分の知識になったと思います。(N様)
・ 今まで会議等でPL、BSなど見る機会はあるが、何となく理解している感覚であったが、間違っているところもあった。自信を持って会議に参加できる。自己資本比率が高いと安定の意味が良く分かった。(石原様)
・ 分かり易く、社内で話をする時に使えそうな表現が多々ありました。所々自分が本質的に理解できていなかった部分を気付かされ、学びとなりました。(山内様)
・ BSとPLの見方も分からずいましたが、分かり易い例をあげて頂いたので、スーッと入ってきました。感謝申し上げます。(O様)
・ お客様とお話する際に、このようにお話をさせて頂けば理解が早くなるのではと勉強になりました。難しい言葉よりも、分かり易い日常生活で使うような言葉が、興味の一歩。ありがとうございました。(G様)
ご参加頂いた皆様、ありがとうございました!次回は年明けに開催予定。初の週末開催を考えております。乞うご期待!


2015年
8月
31日
月
ご要望にお応えしてセミナー開催します!(11/4水)
前回、ほぼ全ての参加者の方から「分かり易い!」という好評価を頂いた、「経営者の為の決算書の読み解き方」セミナーを、再度開催致します!
自社の決算書を片手に、その構成を学んで頂けます。個人がローンを組んで住宅を購入するケースを例に取り、それを会社に置き換える形式で進めます。
「営業は得意だけど財務はどうもなぁ」「財務が重要だと分かっては居るけど、学ぼうとするといつも躊躇してしまう…」「何とかスタートしても、専門用語が多すぎて挫折…」という、経営者の方及び次期経営者の方におススメです。
決算書に馴染みの薄い方を対象としています。
11月4日(水)13:30~16:30、名駅プレミアホール(名駅徒歩3分)にて。詳細はコチラ
2015年
8月
19日
水
セミナー開催しました!

セミナー「~自社の決算書を片手に学ぶ~経営者としての決算書の読み解き方」を開催しました!
「財務には正直、殆ど触れてきていない!」という経営層の方を対象にして、個人が住宅ローンでマイホームを買うケースを例にとり、それを会社に置き換えて、自己資本比率や減価償却費などを解説。その都度自社の決算書を確認して頂き、自社の財務上の理解を深める、というスタイルをとりました。
「財務」「決算書」というと、どうしてもとっつきにくいイメージがありますが、省略するところは大胆に省略し、「個人がマイホームを買う」という身近な事例で解説したことで、「分かりやすい!」との声を多数頂きました ^ ^。中には「とても分かり易く噛み砕いて教えてくれるセミナーをずっと探しておりました」というご意見も!
以下、皆様のご感想です(一部抜粋)
-
一つ一つの表現の仕方と説明文が分かりやすかったです
-
とても分かりやすかったです。(資料の構成と内容、プレゼンスキルの両面で。)
-
やさしく説明して頂いたので、分かりやすく、ためになりました。
-
B/Sの理解が大変深まりました
-
経理の関係で売掛が増えるのが悩みでしたが、B/Sを見れば意味が分かったので納得しました
-
全く無知でしたが、基本的な事からしっかり聞くことができたので、今現在では十分理解できました
-
具体例が良かった
-
大変分かりやすく勉強になりました。倍の時間を掛けてより詳しく教えて頂きたいと思いました。
-
今まであやふやなままで決算書をみていました。経営は全て数字なので、より細かく今後は見ていく為の分かりやすい解説、ありがとうございました。
-
とても分かり易く噛み砕いて教えてくれるセミナーをずっと探しておりました。今日受けてみて、自分も(経営者として)やっていきたいというモチベーションが上がりました。
-
全体的に非常に丁寧に分かり易く説明をして頂いたので、分かりやすかったです。専門用語も少し知ることができました。まだまだ分からないことばかりですが、楽しいと思えるセミナーでした。
-
とっても分かり易くて、財務諸表をこれから見ていく切っ掛けになりそうです!
次回は10月~11月頃に開催を考えております。またFacebook上で告知させて頂きますね!
2015年
8月
06日
木
御社の部門損益はちゃんと「活きて」いますか?
(3)ベクトルはこうして合わせる!
「従業員が思ったように動いてくれないんだよなぁ。少し考えれば分かるハズなんだけど…」
経営陣の方から良く耳にする言葉です。社長自身の在り方や従業員との関係性、そもそも上記の様な「従業員を動かす」という姿勢自体がどうなんだ!?という視点は一旦置いておいて、ここでは「経営陣と現場従業員の方とのベクトルを合わせる」という見方で。
さて、もし上記の様な悩みがおありなら、まず確認してほしいことは、「取ってほしい行動/やってはいけない行動が、社員に分かる形になっているかどうか」ということ。典型的には、望ましい行動が文書化されていて、実行した社員を褒める、公表する、表彰する、インセンティブを与える、など(逆も同じです)。
・・・ココまでだと、まぁ「良く聞く話」ですよね。ここで加えてお伝えしたいのは、それらの「取ってほしい/やってはいけない行動」を、戦略的に会計に落とし込む、という事(一般論ではなく当社推奨スキームです)、そしてその会計をしつこく運用していく事、です。
例えば、、、
-
通常は出荷や検収時点でしか計上できない売上を、契約時点で50%計上する
-
社外向けではなく部門間の「出荷」も売上として計上する
-
リユース業界なら、買い取り(=仕入)に対して収益計上する
-
もっと大胆に、例えば「優秀な人材を紹介して入社に繋がったら100万円の収入、逆に失望退職を招いたら100万円の損失」としてしまう
-
人材を育成して他部署に送り出したら、異動先から異動元に50万円を「支払う」
-
お客様からの感謝の手紙は10万円の収益にする
-
クレームは1件10万円のペナルティだが、それを次の購買に繋げれば50万円プラスする
などなど。会社や部署の性質に応じて、かなり自由に設計できます。通常の会計の売上に直接関係しない部門(製造や管理部門)さえ、部門別会計によって利益を計上できる様な作りこみをする事も可能です。
※ 勿論、社内用の会計なので、粉飾などには当たりません。下記3.の項をご参照下さい。
ここで重要な事は3点。
1.「その部門の役割を果たしたら利益が上がる」形に作りこむこと
もっとも基本的な事は、その部門の存在意義ともいえる「社内における役割」を果たした時に利益が計上される様にする、という事です。
例えば、中古品売買の会社での買取部門で、とにかく商品を集める事が役割だと定義すれば、「仕入点数に応じて『売上』を計上する」事になりますし、仕入価格もその部門の裁量になっていて安く仕入れる事が役割ならば、「想定売価と仕入値の差額を『売上』として計上する」という事になります。
又、その部門が「一つの会社」として独立したら何が売上になるのか、と考える事も参考になります。
2.本業以外の事はスパイス的に。ダイジなのは「方向性が明示されている」ということ
例えば人材採用や育成に金額を付すのは、あくまで「+α」の範囲で本業をあまりに侵食しない程度に。勿論、採用の重要性が増せば、評価の金額を上げる事は効果的ですが、そのインパクトが大きくなって本業への注力がそがれるのは本末転倒。それよりもここでダイジなのは「何をやると評価されるのか」が明示されていることです。「何をやったからプラス(マイナス)」という事が分かる事で、ベクトルが揃いやすくなります。
3.財務会計との差異を認識しておくこと
ここで述べている事はあくまで「社内用の会計」(いわゆる管理会計)についてです。税務署や銀行へ提出する、通常税理士の方が行う「財務会計」とは別物です。(勿論粉飾などには当たらないのでご心配なく。)ここは、管理部門が脳みそに汗をかいて作りこむところです。
で、例えば通常の会計処理では発生し得ない「人材採用,育成」などについて金額を付けるとすると、財務会計との乖離が出てきます。最も避けねばならないのは、「部門会計上の合計では利益が出ているが、財務会計上では赤字」という状態を招くこと、かつそれに「気づいていない」こと。こういう場合は作りこみが甘いか、その後の管理が甘いかのいずれか、です。
前回までの繰り返しになりますが、部門別会計は上手く運用できれば業績を【劇的に】改善できるパワーを持っています。それには、経営の意図が色濃く反映される様に作りこみ、かつ粘ちっこく運用していく事が不可欠です。
部門損益を元にランキングや表彰、インセンティブへ反映する事も(上手く運用できれば)従業員の方の行動が変わりますし、経営陣と部門責任者が部門損益について常に話し合う機会を持つ、雑談の中で折に触れ言及する、等だけでも、それまでとは違う言葉が現場の方の口から飛び出てくる様になりますよ ^ ^
部門別会計シリーズはこれで一旦終了!です。ご質問等はコメント欄かFacebookで!
【セミナー開催のお知らせ】
主に経営層の方を対象に、財務の初心者向け決算書の読み方セミナーを開催します!
自社の決算書をお持ち頂き(なくても結構です。見本を準備します。)、
セミナーと同時進行で分析して頂きます。
内容は簡単ですが、基本的なところはしっかりとおさえますので、税理士や銀行員と本質的な話ができるようになります。
8月18日(火)13:30~16:30、名古屋駅から徒歩5分のウインクあいちにて。
既に経営層の方、将来の経営層の方、経理担当で「簿記は分かるが決算書は…」という方にお勧めです!
2015年
7月
24日
金
御社の部門別会計は、ちゃんと「活きて」いますか?
(2)組織と会計の整合性
社長、貴社の部門損益はちゃんと「活きて」いますか?
「ちゃんと毎月現場に渡しているけど、責任感が感じられないんだよな。のれんに腕押し状態だよ…」
良く耳にします ^ ^ ;
こんな時、確認して欲しいのは
① 組織図と利益責任が整合しているか?
組織図でのポジションが上になればなるほど、利益責任はPLの下に向かう様になっているか
② その利益責任に応じた権限が与えられているか
ということ。
上記の①を図にすると…
2015年
7月
16日
木
御社の部門別会計は、ちゃんと「活きて」いますか?
(1)部門別会計は人事に行き着く
御社の部門別会計はちゃんと「活きて」いますか?
部門別会計は、バッチリ運用できればそれだけで業績を劇的に(「劇的に!」です!!!)向上させる威力がある一方で、「導入したは良いけど、もはや抜け殻状態…」というケースも^^;
私がこれまで部門損益に携わってきて確信したのは、「部門損益を突き詰めると人事に行き着く!」という事。(←ココ、とっても大事!)
そういう視点で言えば、運用しても効果ナシの部門別会計は、「そもそも人事面が整っていない!」か、「人事制度との整合性が取れていない…」のいずれかです。
例えば…
1.そもそも「組織をどの単位で分けて損益管理するか」という事が不明瞭
部門の区分けが曖昧/組織にダブりあり/やたら兼務が多い…。
→ どの費用がどの部署の負担なの?そもそも部門コードをどう振れば良いの?
という事が起こります。
いくら経理部門が汗をかいても、部門別会計がワークする事は残念ながらあり得ません…
2.部門の利益責任を負う人(例えば店長)が、それに応じた権限を与えられていない
自部署の費用は、ちゃんとその部署の利益責任者が決裁しているでしょうか?
YESなら、決裁する際に「本当に本当に必要?」と思い悩む様になりますが、
NOなら「責任だけ負わされる…」と考えるようになり、やる気ダダ下がり…。
※ 金額で決裁範囲を制限するのは勿論アリです
3.部門の利益を上げても「良いこと」が無い
例えば賞与などのインセンティブや、「ほめられる」という事はなされているでしょうか?
ここが上手くできれば、組織のベクトルは揃います
勿論、中小企業では権限規定なんて無いところが殆ど。そんなにキッチリやる必要はアリマセン。ダイジなのは、「現場の納得感があるか」、そのために、「自分のやった事がちゃんと数字に反映され」「何をどうすれば改善できるかが数字上で分かり」「その対策を実行できる権限が与えられている」という事。
ちなみに、当社の「参謀s」という社名には、この様に顧問先に「片足突っ込んで」仕事をしたい、という思いを込めています。会社を強くするには、財務や税務の視点だけでなく、経営者としての視座が必要。部門別会計を「形式的に」導入するのは比較的簡単ですが、実態を捉えた形に作り上げ、それを血肉化して実際に会社を動かす武器に仕立て上げる、そここそが難所であり、最も面白いところだと思うのです ^ ^
さて、次回は部門別会計第2弾「組織構造と利益責任」について!
【セミナー開催のお知らせ】
主に経営層の方を対象に、財務の初心者向け決算書の読み方セミナーを開催します!
自社の決算書をお持ち頂き(なくても結構です。見本を準備します。)、
セミナーと同時進行で分析して頂きます。
内容は簡単ですが、基本的なところはしっかりとおさえますので、税理士や銀行員と本質的な話ができるようになります。
8月18日(火)13:30~16:30、名古屋駅近くのウインクあいちにて。
既に経営層の方、将来の経営層の方、経理担当で「簿記は分かるが決算書は…」という方にお勧めです!
※
開催1ヶ月前にして、定員30名の内約半数が埋まっています。ご希望の方はお早めにエントリー下さい!
2015年
7月
10日
金
セミナー:「経営者」としての決算書の読み解き方
「重要だと分かっては居るけど、学ぼうとするといつも躊躇してしまう…」
「何とかスタートしても、専門用語が多すぎて挫折…」
決算書の読み方を学習しようとする方の多くは、上記の様な状況に陥ってしまいがちです。
そこで今回、主に経営層の方を対象に、財務の初心者向けに決算書の読み方セミナーを開催します。
自社の決算書をお持ち頂き(なくても結構です。見本を準備します。)、
セミナーと同時進行で分析して頂きます。
内容は簡単ですが、基本的なところはしっかりとおさえますので、
税理士や銀行員と本質的な話ができるようになります。
8月18日(火)13:30~16:30、名古屋駅近くのウインクあいちにて。
既に経営層の方、将来の経営層の方、経理担当で「簿記は分かるが決算書は…」という方にお勧めです!
セミナー詳細、及び参加登録はこちらから!